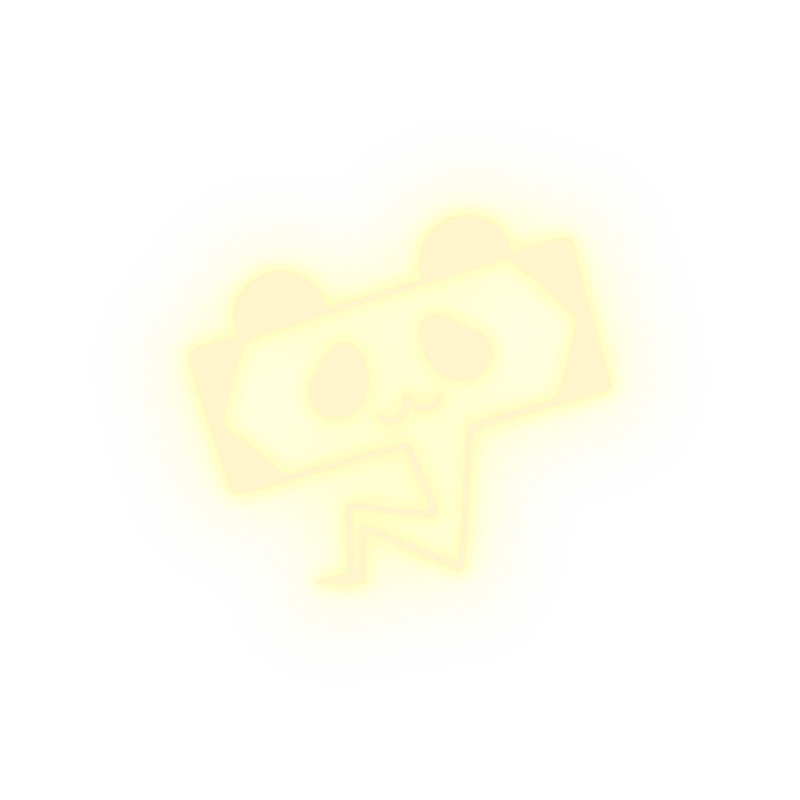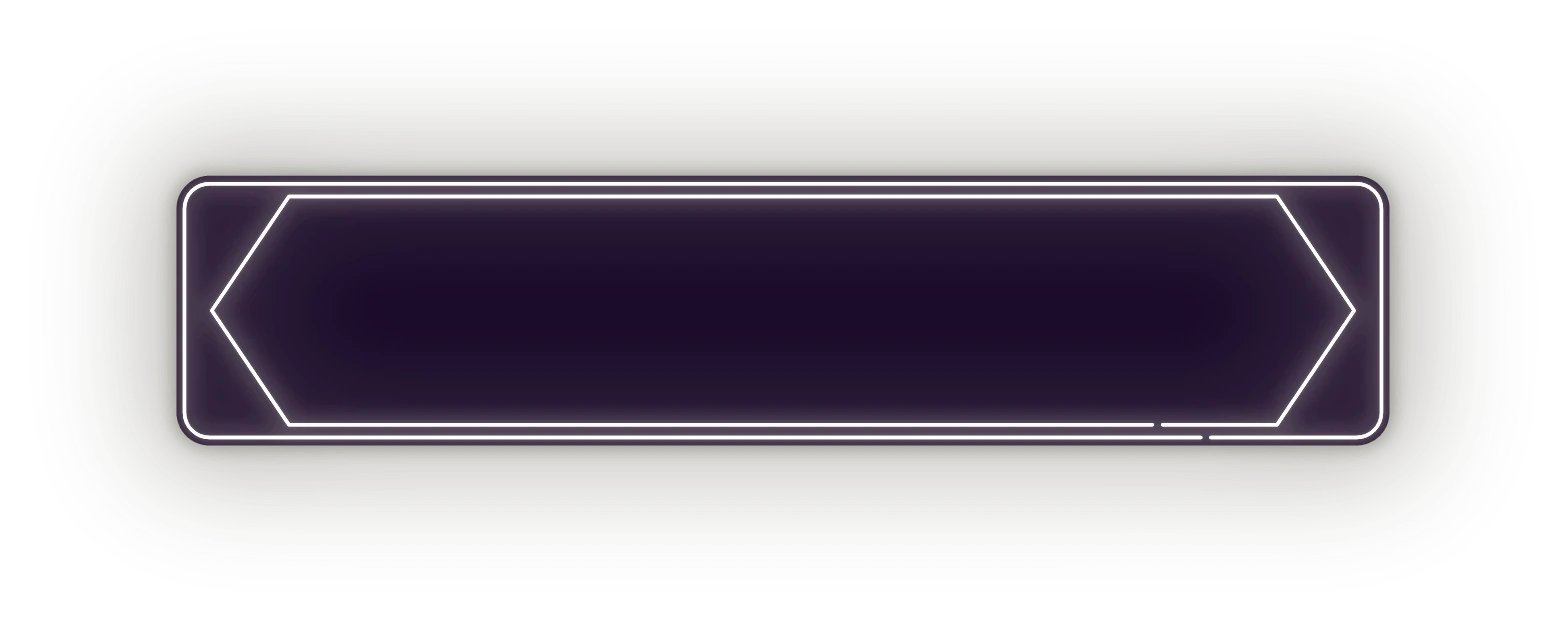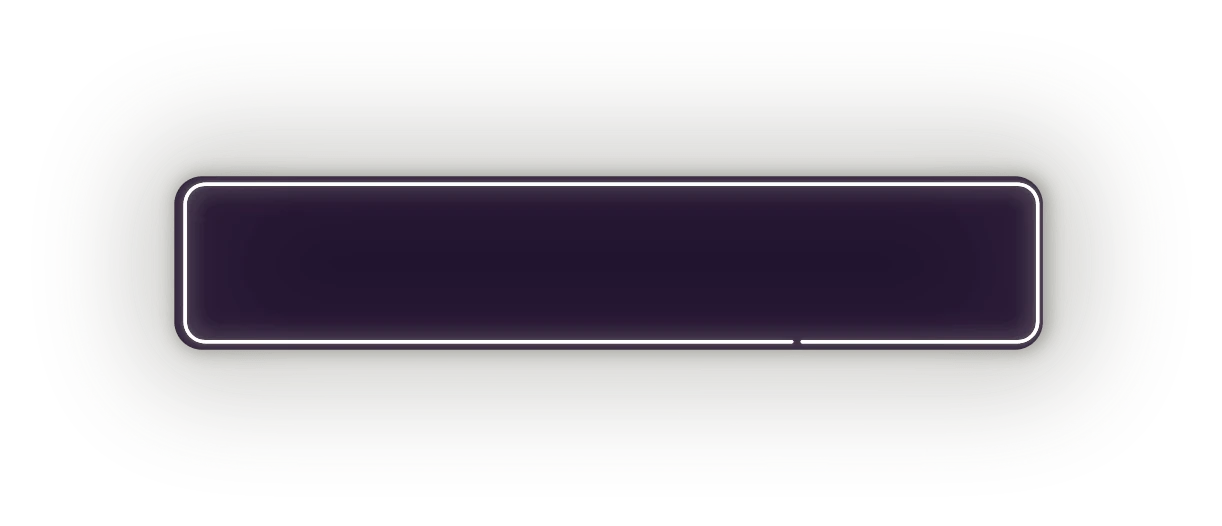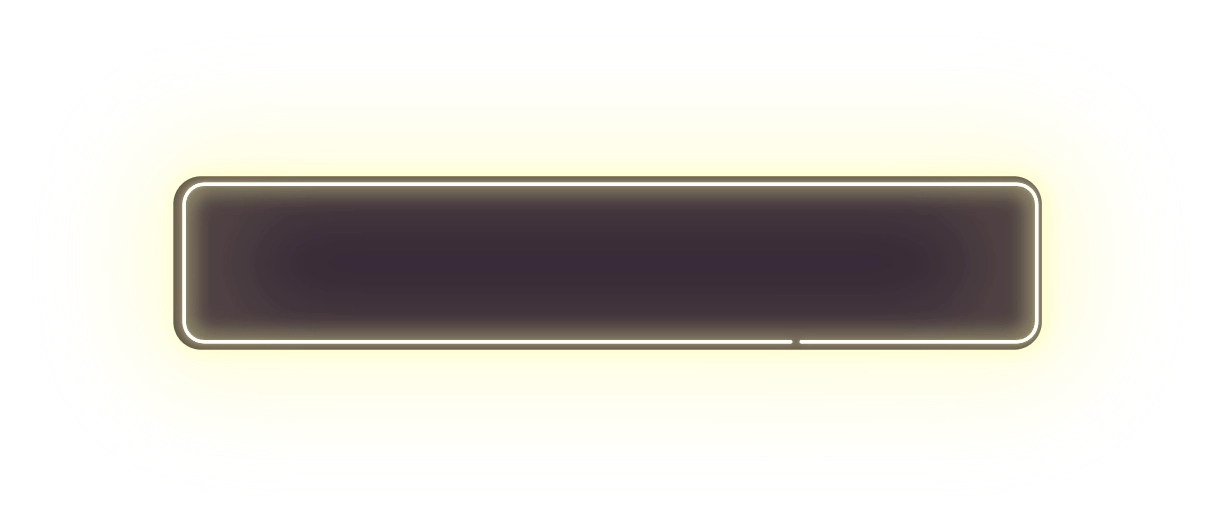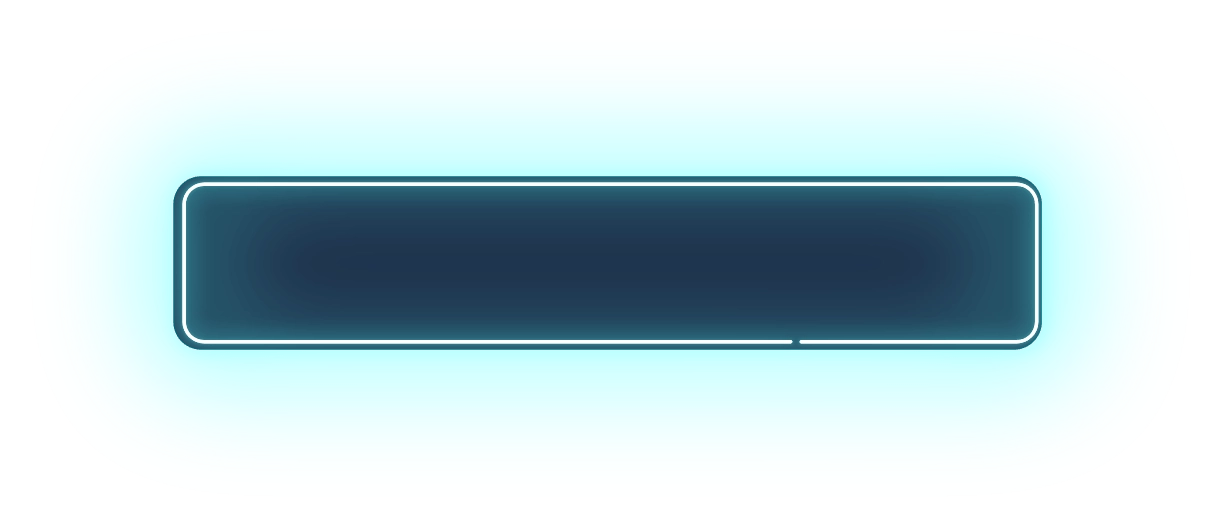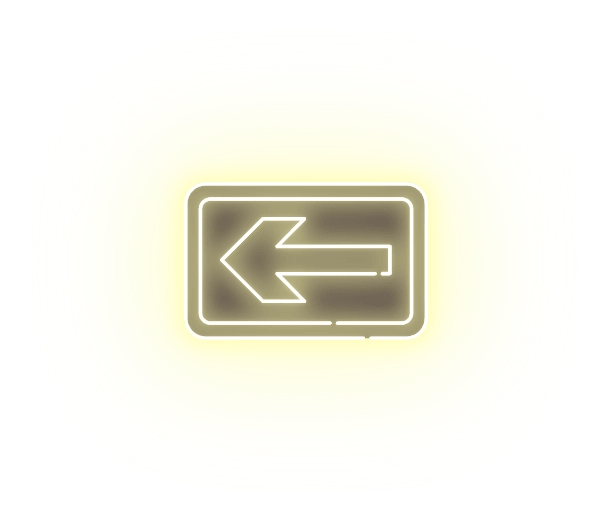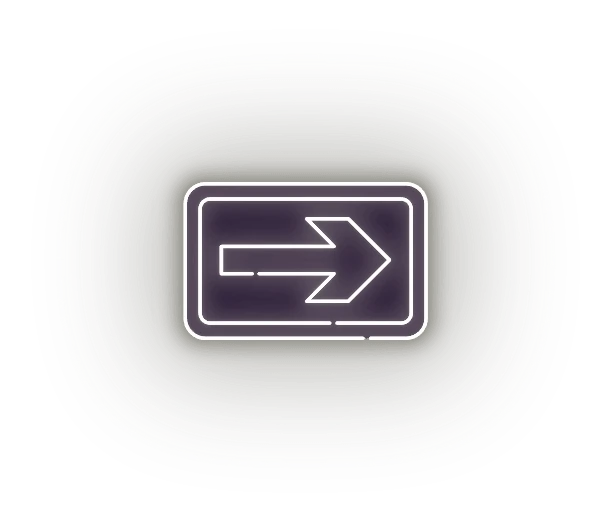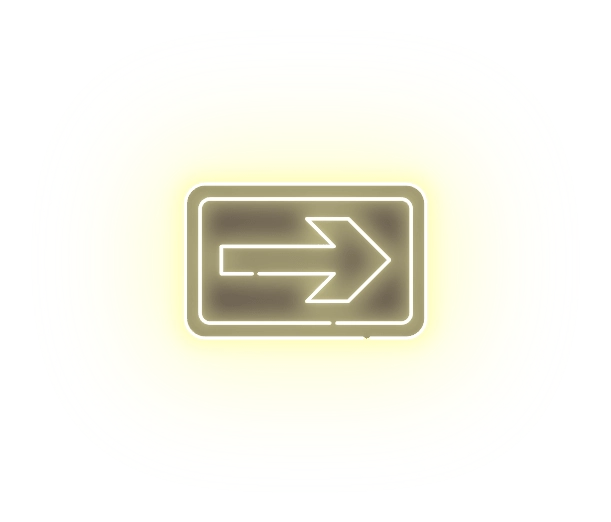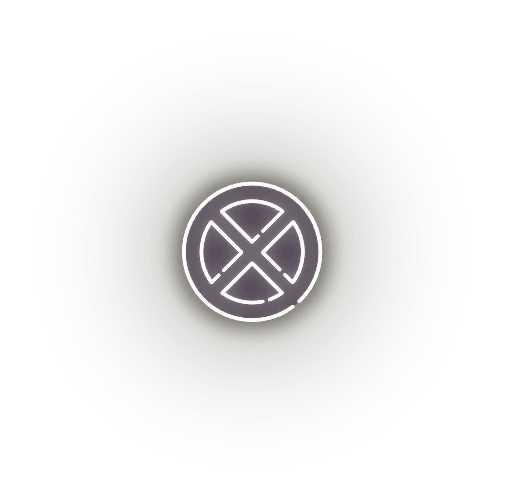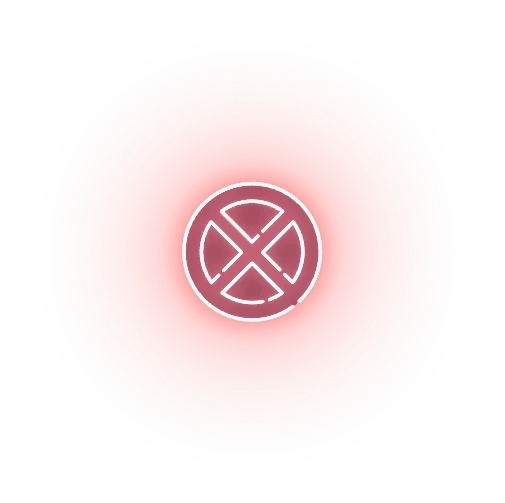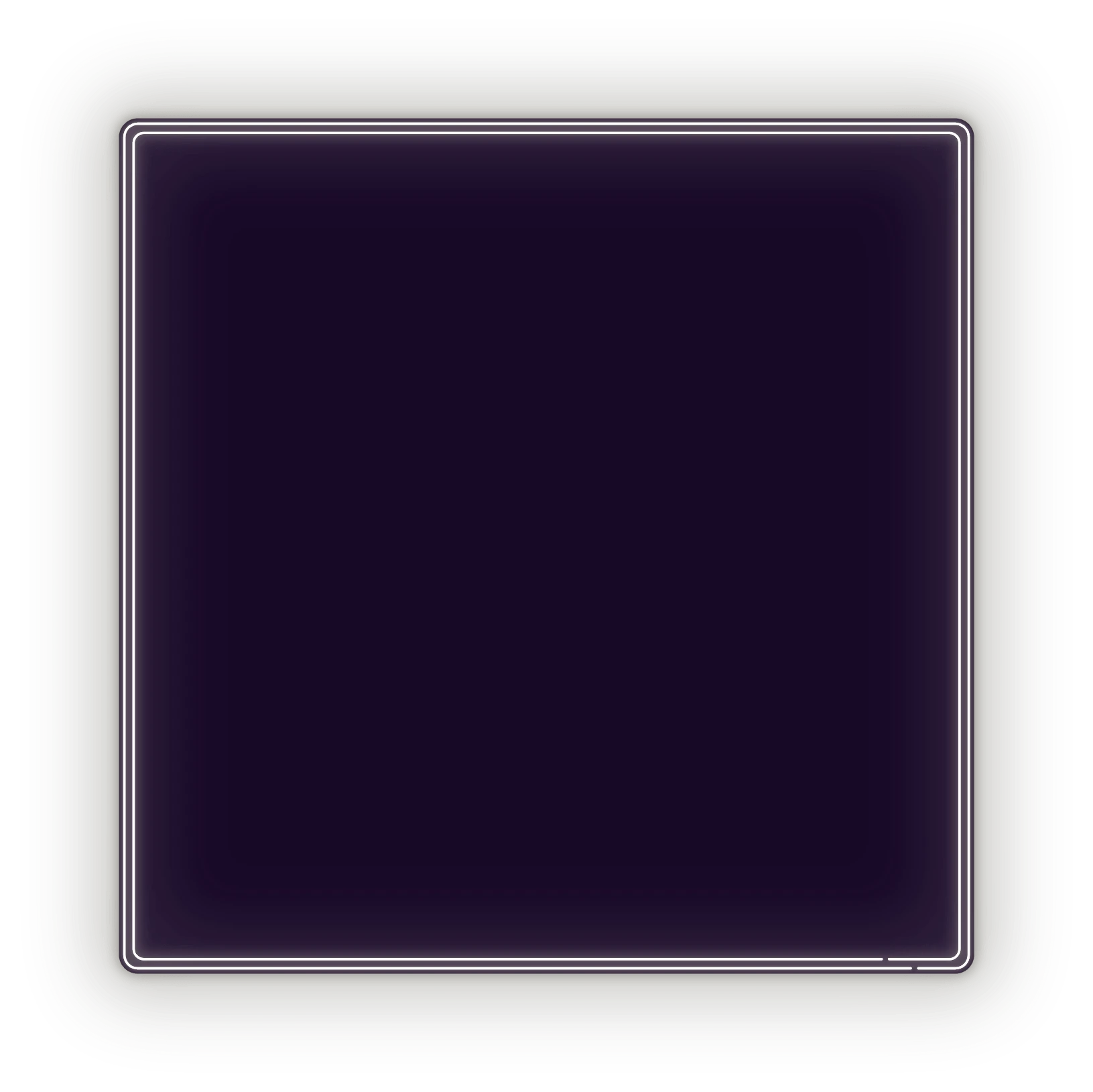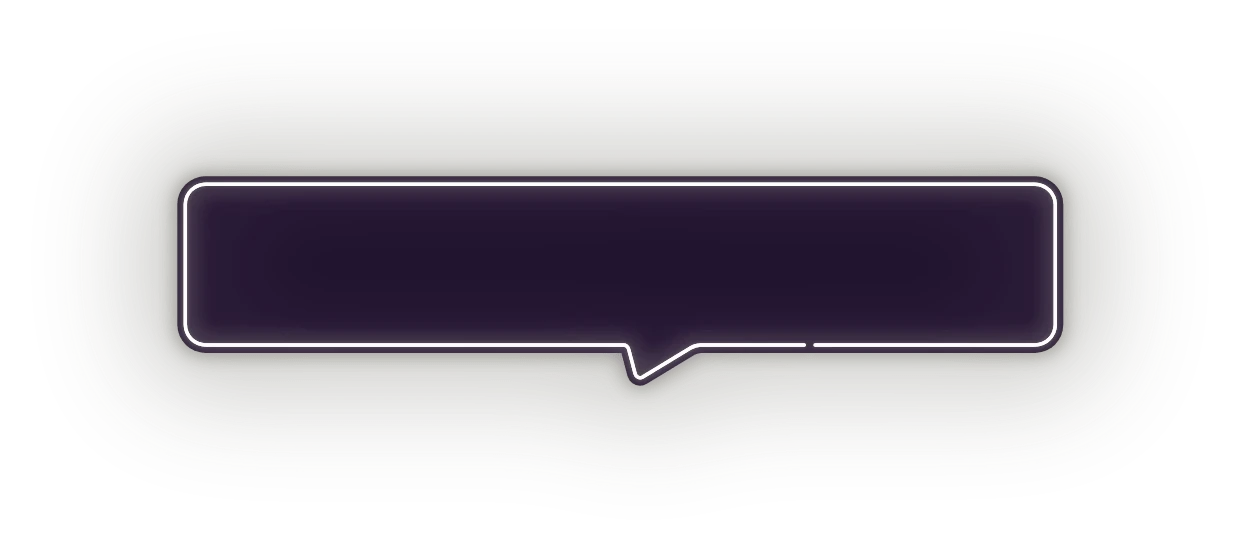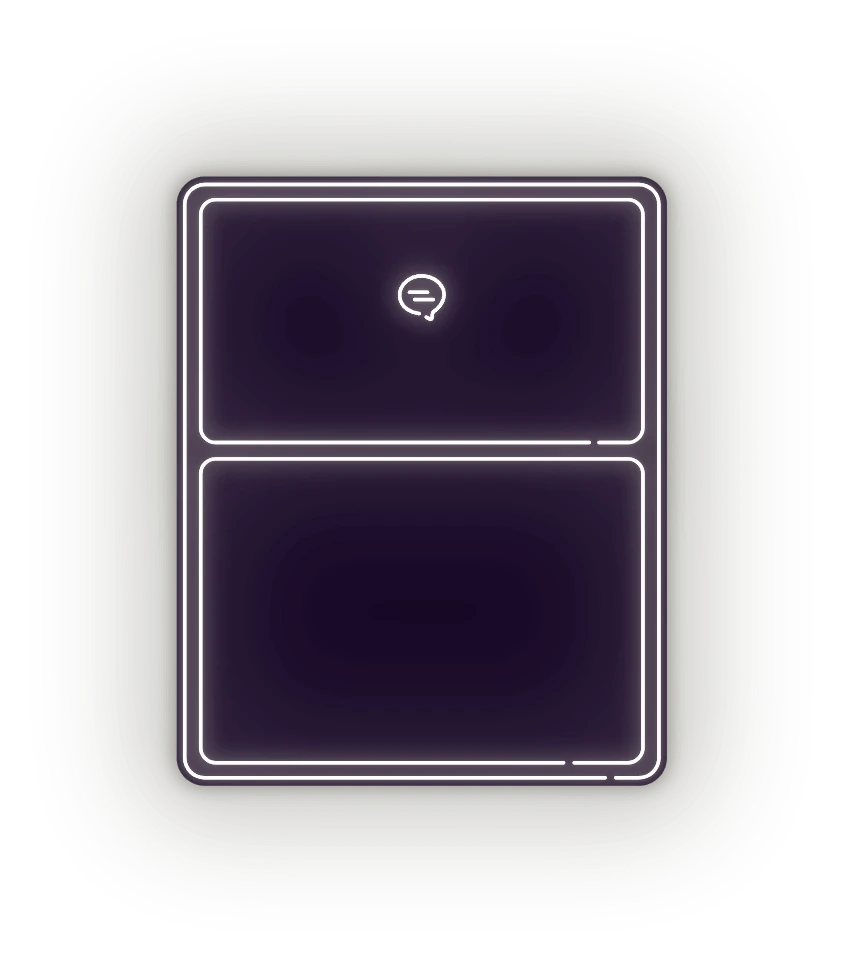広東語って?
広東語、読んで字のごとく、中国南部にある広東省の周辺、主に広州と、香港やマカオで使われている。更には東南アジア、欧米やオセアニアの華人社会を中心に多くの話者が存在している。
と言われても結局中国語じゃんと思っているそこのあなた、それが同じく漢字で書かれてはいるが、方言とか訛りとか以前の問題で、全く違う言葉なのだ。
そもそも文字から違う
一般的に中国語というのは中国の標準語「普通话」、いわゆる北京語のこと。
まず北京語で使われる漢字がそもそも広東語とは違うもので、どのぐらいかというと、同じものからお互いなんとなく読めるものもあれば、わざわざ勉強しないと全く読めないものもある。
北京語、ひいては中国のほとんどの地域では「簡体字」が使われている。それは、現在の中華人民共和国が約70年前に建国した際、より多くの人が読み書きできるように、すなわち識字率を上げるために、古来ある漢字を簡略化したり、簡単に書ける全く別な文字に置き換えたもの。
対して広東語の「繁体字」には未だに昔からの伝統的な文字を使っているものが多く、名前の通り画数の多い複雑な文字ばかり。
ちなみに日本語で使われる漢字にはそのどちらか、または全く別物もある。
いくつかの例を見てみると
愛
愛
爱
会
會
会
竜
龍
龙
広東語では古くて難しいほうの文字を使っているとよくわかる。同じ「竜」のはずなのに、香港の人からすると簡体字の文字がわけが分からない場合もあれば、中国の人からは逆に繁体字が難しくて読めないかもしれない。
ただし同じく広東語を話していても、ややこしいだが、広州では中国の政策によって簡体字を使っている。昔広州の方から繁体字、特に「龍」の文字がすごくかっこいいと言われたことがあって、笑いながらも軽くカルチャーショックを受けたことを今でもよく覚えている。
もちろん発音が全くの別物
日本語にもある「雨」と「飴」、「箸」と「橋」のように、アクセントが変わると全く違う意味の言葉になるものがあるが、それでもほとんどの言葉はアクセントをどこに置いても伝わりにくくはなっても意味が分からないことは少ないと思う。
しかし、広東語でも北京語でも、声調と呼ばれる、文字にはそれぞれ決まった音の高さや発音の仕方があって、それが変われば全く別の文字になるため、話す時にはイントネーションに気を付けないと誤解が生まれやすい。
北京語には4つの声調があって、声調に馴染みがない日本人にとっては初めて習う人から発音が難しいという声もよく聞く。
対して広東語には基本となる声調が6つ、分類法によっては9つもあるとされている。北京語に比べて更に細かく、ほんの少しズレるだけで違う言葉になってしまう。それが広東語の難しさの理由でもある。
結局のところどう違うのかは、実際聞いたほうがよくわかる。
ただし、多くの日本人が苦戦する北京語の舌を巻きながら出す音や喉から出す音は広東語にはないため、発音すること自体の難易度としては広東語のほうが簡単かもしれない。
語彙にまで大きく違う
それでも文字がほとんど一緒だからわかるじゃない?と思っている人もいるかもしれないが、それがそうでもないのだ。
「言葉は生き物」とよく言われるように、ルーツは同じだとしても、その土地の歴史や文化、生活習慣などによって変化していく。広東語ももちろん例外ではない。
特に香港の場合、長い間イギリスの植民地となっていたことから、文化に大きな影響を与えたことはもちろん、香港の広東語には英語の発音や意味からできたものも多い。
例えば「バス」と「タクシー」のことは、香港では英語の音訳「巴士」と「的士」と言うが、中国では「公车」と「出租车」と全く違う言葉で呼んでいる。
他にはややこしいなものだと乳製品の名前が挙げられる。「チーズ」の場合、香港ではほとんど英語からの音訳「芝士」しか呼ばないが、中国語では「起司」や「奶酪」、「乳酪」など様々な呼び方がある。しかし、「乳酪」は広東語ではチーズではなく「ヨーグルト」を意味するため、発音はともかく、文字が同じでも意味が違うさえ存在しているわけだ。
最後に
ここまで読んでいただければおそらく広東語のことを北京語と一緒にする人はいないだろう。
同じ国のはずなのにどうしてここまで言葉に違いがあるのか?と疑問に思う人もいるかもしれないが、それは一言でいうと単純に中国が大きすぎるからだ。
広東語以外にも地域によって様々な言葉が存在していて、そのため中国では標準語とされる北京語に統一しようとしている。その結果、その言葉を使う人が少しずつ減っていくわけで、やがて誰もいなくなるかもしれない。
言葉とは大切な文化の一部で、日本でもアイヌ語のような途絶えてしまって、現在は文献や資料としてしか知られない言葉があるように、そうならないようにも、まだ間に合う今だからこそできることをすべきなのだ。
学ぶなら「粗口」から?
語学は悪い言葉から学ぶとよく言われるが、それが正しいかどうかはともかく、口調のせいなのか実際全く知らない言葉でも、悪口のほうが記憶に残ることは確かにある。いざ怒られてもわかるから、たとえ話すことはなくても知っておいて損はないはず。
広東語にはスラング、特に人を罵倒するためにある、「粗口」と呼ばれるものが非常に多く、汚い言葉のバリエーションの豊かさなら世界トップクラスとも言われる。
悪口にもレベルがある
他の言語を知らないとあまり実感がないかもしれないが、日本語は世界的に見ても悪口が少なく、例えば英語圏でよく使われる「Fuck(ファック)」でも、日本語では該当するような言葉がない。
他の言語の悪口を日本語に翻訳しても、「くそ」や「畜生」等、同じような言葉になりがちで、ある程度以上になると、そのニュアンスを表現できるレベルの言葉がなかなか見つからないのだ。
特に広東語の場合はその悪口の多さから、相手を軽くからかうものから、人が聞いたらすぐ顔色が変わってしまう放送禁止用語まで、汚さと言うべきか、口調の強さに様々なレベルのようなものが存在する。
そしてそのレベルがどのくらいなら「粗口」に当たるのか、その線引きは人によって様々で、はっきりとは定まっていないのだ。
悪口なら何でも「粗口」として許せない潔癖症と呼ばれるような人もいれば、あまり酷くないものなら口にする人もいる。人を罵る以外にも、強調するためにも使えるから、「粗口」だと知りながら日常的に使っている人もいる。
定義の曖昧さに一番困るのが、実は香港では地下鉄をはじめとした公共交通機関、体育館や病院など、公衆の場で「粗口」を話すことは犯罪行為に当たるが、その言葉は「粗口」に該当するかは警察や裁判官の一存によって変わってくる。
ここからは、個人の主観によるものではあるが、そのレベルとともに広東語の「粗口」をたっぷりお届けする。
「粗口」の五大文字
まず確実に言い逃れができない、入っていれば「粗口」として扱われる五つの文字がある。使い方は様々だが、共通として全部性的な意味のある言葉で、聞くに堪えないと思う人がほとんどだと思うが、一番使われる「粗口」でもある。
これらの言葉は古くから存在しており、正しい文字なのかは既にあやふやで、「粗口」であることからネットでの制限等を回避するために、様々な代用の文字や言い方が生まれている。
屌
diu2レベル: ★★★★★
おそらく五つの中でも使う頻度が一番高い「屌」、俗的に「𨳒」とも書く。意味回避として発音の近い「妖(yiu2)」や「小(siu2)」とも言う。
元は名詞で男性器を意味するが、現在では性行為の動作そのものを指す動詞として使われることが多く、「粗口」としては口調を強くするための感動詞でもある。
多くの場合はそのままの意味ではなく、相手の性別を問わず、犯してやりたいくらい怒っていることを表す。
他には特に本来の意味とは関係なく、驚いた時や、特定の相手のない不満を表す時にも、それから相手を非難するという意味で動詞としても使われる。
「屌」の一文字で使うことも少なくないが、一般的には「屌你老母」という慣用句で使われることが多く、更に派生としてその頭文字を取った「DLLM」、「屌那媽」や「屌那星(吊那星)」等もある。
ちなみに台湾では非難するどころか、「凄い」、「強い」等の意味を持つ褒め言葉として使われる。
撚
nan2レベル: ★★★★★
「撚」とは男性器のことで、俗に「𨶙」とも書くが、正しくは「𡳞(lan2)」と言われる。近年ではネット上では「L」と書かれることも多い。
単体で使うことはほぼなく、強調したり、悪口を更に強くするために言葉の間に入れることが多い。例えば「すごく良い」という意味の「好正」の場合は「好撚正」となり、「役に立つ」という意味の「有用」は「有撚用」となって、「使えない」と反対の意味になる。
「大檸樂」もその派生の一つで、使える範囲が非常に広い。
それからよく使う慣用句としての「撚樣」は読んで字のごとく、直訳すれば「男性器のような顔をしている人」という意味で、嫌な男性を罵るための言葉となる。
他には「フェラ」のこと、ひいては「トラブル」や「大変なことになる」を意味する「含撚」や、「やる意味がない」、「やる価値がない」ことを「把撚」という。
ただし広東語には「撚手小菜(得意料理)」や「撚化(からかう)」等、「撚」を使っているが「粗口」として扱われないものもある。
鳩
gau1レベル: ★★★★☆
「鳩」本来は「㞗」と書くと言われ、俗に「𨳊」、時々「尻」とも書かれるが、ハトでもお尻でもなく、男性器、特に勃起したものを意味する。ネット上では数字の「9」や、プラスチックという意味の「膠(gaau1)」で代用されることも多い。
「撚」と同じように、単体よりも強調するために言葉の間に入れて使うことが多い。
よく使われる言葉として「做乜鳩」があって、直訳すると「何をしている?」になるが、「意味わからん」という意味で、代わりに頭文字を使った「jm9」として書くことが多い。
それから「アホ」という意味の「戇居」を強くした「戇鳩」もよく言うが、字が難しいためか多くの場合は「on9」や、発音の近い「硬膠(硬いプラスチック)」と書く。
他にはギャラリーで紹介された「鳩嗚」や、動詞の前に付けて、意味や目的等がよく分かっていないまま、適当に何かをすることを意味する。例えば「分からないのに適当に答える」ことを「鳩答」という。
柒
cat6レベル: ★★★★☆
数字の七の古い書き方である「柒」は借りた文字で、本来は「杘」や「𨳍」と書くという。発音も数字「七」である時(cat1)よりも低い。
「鳩」と同じく勃起した男性器を意味するが、特に硬くならないものと指すと言われ、転じて「バカ」や「のろま」、「役に立たない」、更には「格好悪い」、「恥さらし」、「醜い」等の意味で使われる。
前述の意味で形容詞として使われる場合が多く、強調のための助詞としても使うこともあるが、「撚」と「鳩」に比べて頻度は少ない。そのため「粗口」五大文字の中でも使用率が一番低いかもしれない。
「柒頭」の他に、バカの意味をで更に強めた「柒頭柒腦」や「碌柒」、それから「把撚」と似た意味の「托柒」等がある。
閪
sai1レベル: ★★★★☆
「閪」とは五大文字の中で唯一女性器を意味する言葉で、正しくは「屄」と書き、「ハイ」と発音するが、現在では「西」と書いて「サイ」と言う人が多い。
「撚樣」とは対になるような言葉で「臭閪」があり、主に女性を罵倒するために「閪」が使われる。
基本的には「柒」と同じく、「ずる賢い」や「性格が悪い」等の意味の形容詞として使われることが多く、強調に使うことは少ない。
「不機嫌そうな」を意味する「黑面」を更に強くした「閪面」もよく使われる。
他にも何かを「台無しに」、「失敗した」との意味があるが、現在ではあまり使われない。
広東語の「粗口」とは基本的にはこれら五つの文字を使った言葉で、更に組み合わせて使ったり、別の言葉で代用したり、更には「童子軍跳彈床」のようななぞなぞまで作られるため、驚くほどの「粗口」の多さになったかもしれない。
「粗口」?悪口?どっち?
これら以外でももちろん様々な悪口や汚い言葉があるわけで、ただし悪口として一番レベルが高いともいえる「粗口」に該当かは本当に人それぞれで、その中でも乱暴なほうで、少なくても公衆の場では控えるべきなものをいくつか紹介する。
仆 街
puk1 gaai1レベル: ★★☆☆☆
表面的な意味としては「道で転んだ」だけだが、本来はヤクザが使う言葉で「野垂れ死ぬ」との意味で、現在では何か悪いことをした人を罵るためか、「ヤバい」や「大変」等の意味で使われる。「仆你個街」や、頭文字を取って「PK」とも言う。性的な意味は一切ないため、「粗口」として扱うか放送業界でさえ非常に微妙な立場にある。更に口調の強い「死仆街」もある。
粉 腸
fan2 cheung4レベル: ★★★☆☆
実際にある豚の腸の一部を使った料理だが、実は発音が近いことから「撚樣」の代わりとして使われる言葉。乱暴な言い方ではあるが、「撚樣」よりは少しだけ軽い感じもするため、「粗口」ではないと思う人もいる。飲茶でよく食べられている「腸粉」と間違わないように。
瞀 里
mau6 lei5レベル: ★★★☆☆
同じ発音で「茂理」「茂利」等とも書く。語源については定かではないが、昔の人が見慣れない西洋建築に驚いて棒立ちしまうことから、英語の柱を意味する「mullion」の音訳でできた言葉という。それから「無知」という意味の「瞀」と、「大鄉里(田舎者)」の「里」が組み合わさった言葉とも。どちらにせよ、「バカ」や「世間知らず」等の意味で、人を見下すような言い方。性的な意味はないが、乱暴に聞こえるからか、「粗口」だと感じる人もいる。
蛋 散
daan6 saan2レベル: ★★★☆☆
ギャラリーで紹介されたため説明を省く。言葉自体はそこまで乱暴な気がしないが、「粗口」をよく言う人から発することが多いため、「粗口」だと感じる人もいる。
頂 你 個 肺
ding2 nei5 go3 fai3レベル: ★★☆☆☆
ギャラリーで紹介されたため説明を省く。基本的には「屌你老母」と同じような使い勝手で、軽いノリで使われることが多く、「粗口」なのかは人による。
冚 家 剷
ham6 ga chaan2レベル: ★★★★☆
「杏加橙」の元の言葉。本来の意味があまりにもたちが悪いため、五大文字は含まれていなくても「粗口」に分類されることがほとんど。同じ意味で若干柔らかく感じる「冚家拎」も同じく「粗口」だと思われる場合が多い。
よくある悪口まで一挙大放出
「粗口」だと思われることはあまりないが、日常的によく使う広東語の悪口もいくつか紹介する。
痴 線
chi1 sin3レベル: ★☆☆☆☆
「黐線」とも書く。「線がくっ付く」と読めるが、実は「頭がおかしい」という意味。同じ意味で更に強い「痴孖筋」もある。
白 痴
baak6 chi1レベル: ★☆☆☆☆
低 B
dai1 Bレベル: ★☆☆☆☆
2つとも「知能が低い」、つまりは「バカ」という意味で、「低B」の「B」は英語「Brain(脳)」から来ているという。小学生でさえ使うような軽い悪口。
食 屎
sik6 si2レベル: ★☆☆☆☆
読んで字のごとく「クソを喰らえ」という意味。「引っ込め」というニュアンスで使われることが多い。口調を少し柔らかくした「食蕉」という言葉もある。
八 公
baat3 gung1レベル: ★★☆☆☆
八 婆
baat3 po4レベル: ★★☆☆☆
本来は「八卦」な男性を「八公」、女性を「八婆」と言うが、いつしか単純に人を罵るための言葉となった。少し乱暴な言葉ではあるが、「粗口」とされることは少ない。前に「死」を付けて「死八公」、「死八婆」と更に強めた言い方もある。
廢 柴
fai3 chaai4レベル: ★☆☆☆☆
「燃えない薪」、つまりは「役立たず」、「使えない人」の意味で、近年では相手のことを指すよりも自虐として使うことが多いかもしれない。
你 老 闆
nei5 lou5 baan2レベル: ★★☆☆☆
テレビドラマのセリフにも使われるくらい「粗口」とはされていないが、実際は「屌你老母」と同じような意味で、少し柔らかくなった「屌你老味」から「屌」を取り除いた「你老味」を、更にオブラートに包むような言い方。ちなみに「老闆」とはボスや上司のことだが一切関係はない。
使う相手や場所は慎重に
ここまで様々な悪口を見てきて、さすがにお腹いっぱいになっている人もいれば、使ってみたい人もいるかもしれない。
「粗口」を含め、広東語での悪口はかなり軽いノリや冗談で言ってしまう人もいるし、意味等関係なく口癖のように言っている人もいる。
それでも「口は災いの元」というように、もちろん全員が全員そうとは限らない。軽くからかうつもりで言っても、そういった言葉を一切使わない人に引かれたり、怒られたりする可能性も十分にある。
前述したように場所によっては罪を問われることもあるため、話す前にしっかり相手や時と場合を考慮すべきなのだ。
「水」の七変化
日本語には同じ発音で違う漢字と書いて違う意味を持つ、いわゆる同音異義語がたくさんあるが、広東語には同じ漢字なのに全く違う意味を持ち、発音さえも微妙に違う場合もある、同字異義語が多く存在している。
とりわけ広東語の訳がわからないほどの難しさがよくわかると言われるのが、「水」なのだ。
「水」の一文字だけでもいくつかの意味を持っている上、「水」を使った熟語は驚くほど多く、意味もバラバラでなかなか掴めないが、それこそ広東語の面白いところでもある。
「水」に関しては、昔の香港映画《七十二家房客》にはちょっとした有名なセリフがある。
「 有水有水,冇水冇水。
有水過水,冇水散水。」

消防士から発したそのセリフは、「お金あるなら水はある、なかれば水はない。お金あるなら出せ、なければ帰る。」という意味で、昔の消防士の汚職事情を物語っている。
そんな奥深いセリフができる広東語の「水」の様々な姿を、ぜひ楽しんでいただきたい。
液体としての「水」
まずは本来の「水」の意味とも近い、何かしらの液体の名前として使われる「水」から。
口 水
hau2 seui2口から出る水、つまりはツバ、唾液のことだが、それ以外にも喋るという意味で使われる。例えば「口水多過茶(お茶よりもツバが多い)」は喋りたがりや話が長い、口だけの人の意味で、「嘥口水(ツバの無駄使い)」は言うだけ無駄という意味になる。
汽 水
hei3 seui2「汽(気体)」の入った水は、コーラやファンタ等の「炭酸飲料」全般を指す。「空氣(空気)」は「氣」なのにどうして「汽車」の「汽」なのかは不明。ちなみにラムネのことはビー玉(の入った)炭酸、「波子汽水」と言う。
糖 水
tong4 seui2砂糖水ではなく、酒席等のコース料理の最後に出される、スープ状のデザートの総称。香港にはレトルトやインスタントの「糖水」や、お店での食事の後に行く「糖水」をはじめとした様々なデザートを提供する店がたくさんある。ちなみに現在では全然使われないが、昔ラブホに行くことの隠語として「食糖水」という。
凍 滾 水
dung3 gwan2 seui2「冷たい沸騰する水」と少し不思議に聞こえるが、香港では味以前の問題で水道水はそのまま飲んではいけないため、一度沸かす必要がある。そのあと冷ました飲み水や料理等に使う水を「凍滾水」と呼ぶ。ちなみにレストランや街中で、「どいて」という意味で「滾水」と大声で叫ぶ習慣は今でも時々見かける。
倒 汗 水
dou2 hon6 seui2蒸し器や鍋蓋の裏につく水滴のことや、窓やエアコン等の結露のこと。汗とは関係ない。
例 水
lai6 seui2「運吉」で紹介されたように、昔は「湯(スープ)」のことを「水」と呼んでいた。「例水」とは今の「例湯」で、「茶餐廳」等で注文した後に無料で提供される日替わりスープのこと。
滷 水
lou5 seui2「鹵水」とも書く。香港のみならず広東一帯で用いられる、醤油をベースに山椒や八角等の香辛料を加えた調味料「滷水汁」を使い、味を染み込ませるために煮込んだものを、「滷水◯◯」または「滷味」と言う。
火 水
fo2 seui2「火がつく水」と書いて、無色透明でまるで水のような「煤油(ケロシン)」の俗な言い方。ランプや料理等、家庭でも広く重宝されていたが、現在ではほとんど使われない。
鏹 水
keung5 seui2硫酸や塩酸等の腐蝕性のある強い酸のこと。昔では個人的な報復や、マンションから投下するテロめいた事件等、「鏹水」を使った犯罪行為が多発していたが、近年ではあまり聞かない。
天 拿 水
tin1 na4 seui2塗料等に使ううすめ液、シンナーのこと。英語「Thinner」の音訳で、香港ならではの呼び方。
古 龍 水
gu2 lung4 seui2「古竜の水」など大層な名前が付いているが、コロンの英語「Cologne」の音訳からできた言葉に過ぎない。コロンという厳密にいうと香水の一種だが、香港ではイメージ的に男性用の香水を指す。
蚊 怕 水
man1 pa3 seui2怖いどころか蚊は水のある場所で繁殖するのに、直訳すると「蚊は水が怖い」というのは、液体タイプの虫除けのこと。
龍 舟 水
lung4 jau1 seui2「龍舟」というのは端午の節句に漕いだり、レースをしたりする、竜の形をしたボートのこと。「龍舟」が通った後の水には幸運をもたらす、子供の成長を促す等の効能があると昔から信じられているため、その水を浴びたり、中で泳いだりするのが端午の節句の習わしの一つ。
神 仙 水
san4 sin1 seui2使えば若返ることができる「神様の水」として、昔はスキンケア用のコスメのことを「神仙水」と呼んでいたが、現在はほとんど言わなくなった。ちなみに近年SK-IIの商品の名前に採用された。
お金としての「水」
「磅水」のように、広東語の「水」はよくお金のことを指す。それに関する熟語も非常に多い。
疊 水
dip6 seui2お金をはじめ、財産が多いという意味の形容詞。現在ではあまり聞かない。
回 水
wui4 seui2払い戻すこと。多くの場合は「退錢」と言い、「回水」は少しクレームっぽく、俗を感じる言い方。
補 水
bou2 seui2残業代、または残業代を支払うこと。ちなみに香港では残業することを英語「Overtime」から「OT」と呼ぶ。「OT」への「補水」は法律上の規定があるわけではなく、会社によってあったりなかったりする。
踱 水
dok6 seui2撲 水
pok3 seui2「踱水」とは誰かからお金を借りること。更に「撲」はあちらこちらを飛び回ることで、貸してくれる相手を探し回ること「撲水」と言う。
昆 水
kwan1 seui2掠 水
leuk1 seui2「昆水」とはお金を騙し取ることで、「掠水」はお金を奪い取ることを言う。両方とも不当な手段で人のお金を取ることは同じで、ニュアンスが似ているため時々逆に使われたりするが、「掠水」のほうは詐欺等ではなく、例えば故意に値上げをするようなことを指す。
cap 水
cap seui2「cap」とは英語「capture」を略したもので、「昆水」と同じくお金を騙し取ることを意味するが、一度に多くの人から取る場合に使われる。
屈 水
wat1 seui2「屈」には他にも別の意味があるが、ここでは無理やり何かをさせられるという意味で、合わせると「屈水」とはお金を払わされることになる。現在ではあまり使われない。
食 水
sik6 seui2飲み水という意味もあるが、より使われるのは儲けとしての意味のほうで、儲けが多いことを「食水深」と言う。あまり良い意味では使われず、例えば明らかに安く仕入れたものを高値で売りさばくことで利益を得る人を指す。
一 舊 水
yat1 gau6 seui2100香港ドルのこと。200ドルの場合は「兩舊水」、300なら「三舊水」となっていくが、それも900ドルまでで、1000ドルのことは「十舊水」等とは言わない。ぴったり100ドルごと以外でも、ざっくりそのくらいの時にも使う。
吊 鹽 水
diu3 yim4 seui2通常は「点滴を受ける」ことを指す。昔医療に関する知識が普及していない時、点滴をするのは重篤な患者だけだと思われていたことが多く、転じて「吊鹽水」は死にかけの人の命を繋ぎ止めるという意味があり、「お金に困っている」時にも使われる。
豬 籠 入 水
jyu1 lung4 yap6 seui2「豬籠」というのは、昔の農民が豚を閉じ込めて運ぶ時に使う目の粗い竹製のカゴのこと。もしそのカゴが水の中に落ちたら、すぐさま水が流れ込むことから、お金が次々と入ってくる、ものすごく儲かるという意味の例えになり、お正月等によく使うお祝いの言葉。
見 財 化 水
gin3 choi4 fa3 seui2「水」はお金を意味することが多いが、「見財化水」はそのまま「見た金銀財宝が水となって流れていった」との意味で、手に入れられそうな大金がパーになるとのこと。
五 行 欠 水
ng5 hang4 him3 seui2「五行」というのは古代中国で、あらゆるものが金、木、水、火、土の五つの元素からできている説のことだが、実際「五行欠水(五元素から水が欠けている)」は「五行」とは全く関係がなく、ただお金がないことを面白く言うための言葉。
動詞として使う「水」
「潛水」の他にも「水」を使った動詞が多く、意味もバラエティに富んでいる。
吹 水
cheui1 seui2おしゃべりすること。ただし時々確証もないのに適当なことを言うという悪い意味で使われる。
縮 水
suk1 seui2悪い意味でものが小さくなること。本来は服が洗った後に縮む現象を指すが、現在では服以外のものにも使われる。
撈 油 水
lou1 yau4 seui2得することや目先のちょっとした利益を貪るという意味。昔にあった誰かが金も払わずに、商品の豚肉を水で洗って油だけ取った後にお店に返した、という出来事からできた言葉という。
抽 水
chau1 seui2仲介の手数料等、こっそり売上等から利益を抜き取ることを指すが、現在はあまり言わない。その代わりに「抽水」というとセクハラや痴漢と、全く別の意味になる場合が多い。
睇 水
tai2 seui2見張りをすること。秘密裏にする必要があることや、犯罪行為等の悪い意味で使われることが多い。
散 水
saan3 seui2現場から離れるという意味だが、何か良からぬことをしてから逃げることを指すことが多い。それから香港では会社を辞める際に、同僚等に「散水餅」というケーキを配ることで感謝を伝える習慣があるが、あくまでもマナーで強制ではない。
醒 水
sing2 seui2「醒」とは広東語で「賢い」の意味で、合わせると空気を読んで気を利かせること。形容詞としても使える。他には十二分に注意するように促すという意味もある。
通 水
tung1 seui2提 水
tai4 seui2「通水」とは答えを知らない人にこっそり教える、つまりはカンニングのこと。「提水」もほぼ同じ意味だが、答えそのものを教えるよりも、答えが分かるようにヒントを与える場合のほうが多い。
放 水
fong3 seui2「放水」は色々な意味を持っており、一つは男性が小便しにトイレに行くこと。「揸水」とも言う。それから試合等で手抜きやハンデをすることや、意図的に他人に情報を提供することによって、相手が得したり行動しやすくなることを指す。
笠 水
lap1 seui2何かをする直前に怖気付いてやめるや逃げることを指すが、現在はあまり使われない。「縮沙」か、あるいは近年だと「淆底」と言う場合が多い。
游 乾 水
yau4 gon1 seui2水はないが、「洗牌(牌を混ぜること)」の動作が泳ぐのとそっくりなので、麻雀をすることを指す。
潑 冷 水
put3 laang5 seui2何かに熱中している人に「冷たい水を浴びせる」、つまりは水を差して中断させること。
拖 落 水
to1 lok6 seui2誰かを「引っ張って水の中へ落とす」という意味で、本来関係のない、あるいは無事で済むはずの人を悪いことに巻き込むこと。
浸 鹹 水
jam3 haam4 seui2「鹹水(しょっぱい水)」とは海の水の言い回しで、「海の水に浸る」ことは海を渡るという意味で、転じて外国で留学、または生活することを言う。
整 色 整 水
jing2 sik1 jing2 seui2「色水」とは色合いのこと。あれこれをして色合い、つまりは表面だけを整えて中身を隠すことで、芝居等をして格好つけることを指す。
斟 茶 遞 水
jam1 cha4 dai6 seui2「お茶を注いだり運んだりする」、つまりは使用人や下っ端のように雑用係として働くことの意味。
食 住 條 水
sik6 jyu6 tiu4 seui2昔の人は川等の水源を発見すればそれを頼りに生活していくことからできた言葉で、助っ人や流行り、社会情勢等、有利な流れを乗ることを意味する。
埋 街 食 井 水
maai4 gaai1 sik6 jeng2 seui2足を洗うという意味で、略して「食井水」とも言うが、現在ではほとんど使われない。昔の妓楼は川に浮かぶ船として経営していたことが多く、「埋街」というのは船を岸に付けること。陸に上がって、川の水ではなく、井戸の水で生活することが、妓女をやめることの言い回しだったという。
形容詞として使う「水」
「水」を使った形容詞には、まるでこのような水という例えが多く、目に浮かぶような光景ばかり。
威 水
wai1 seui2相手の功績や働きがすごく立派で誇れるものだと感じる時に使う褒め言葉。現在では「威水」としか書かないが語源としては発音が同じで、綺麗な色という意味の「媁水」が正しいという。
倒 水
dou2 seui2本来はバケツに入ってる等の大量の水を捨てることを意味する動詞だが、近年では土砂降りや突然の激しいにわか雨の例えとして使われる。
半 桶 水
bun3 tung2 seui2直訳すると「バケツの半分しかない水」で、物事に対しての知識が浅く、よく分かってはいない状態を指す。ニュアンスとしては日本語の「にわか」に近い。
凍 過 水
dung3 gwo3 seui2「水よりも冷たい」とは状況が非常に悪く、希望が見えない時の例え。時々命の危険にも使われる。語源に関してははっきりしておらず、広東語を使う地方は暖かく、水よりも冷たい、すなわち氷を見る機会がほとんどなかったため、この言い回しが生まれたという。
一 頭 霧 水
yat1 tau4 mou6 seui2「頭の中に霧が漂っている」は訳が分からない、よく分かっていない様子の例え。他の人の言ったことに対して使うことが多い。日本語の「頭にモヤがかかった」と言葉としては似ているが、意味は少し異なる。
唔 湯 唔 水
m4 tong1 m4 seui2スープにしては味が薄すぎて、水というのにも違うような中途半端なものを、「スープでも水でもない」と例えられる。仕事等が完成しておらず適当な状態にある等、悪い意味でしか使われない。
順 風 順 水
seun6 fung1 seun6 seui2風にも波にも恵まれ、運がよく、邪魔も入らず、万事滞りなく進められるという例え。お祝いの言葉としても使われる。
疊 埋 心 水
dip6 maai4 sam1 seui2本来は雑念を片付けて何かに集中して一心不乱に取り掛かる様子を言うが、近年ではあきらめて現状を受け入れることに使われることが多い。
拖 泥 帶 水
to1 nai4 daai3 seui2「泥水を引きずっている」かのように、歩くのがすごく遅い様子に、仕事が遅い、のろまを例えるように使われる。時々考えや決断が遅い、優柔不断な人をも言う。
一 潭 死 水
yat1 taam4 sei2 seui2「潭」は量詞で、「死んだ水」とは流れがなく、ずっと留まっている水で、淀んでいる池や大きいな水溜まりのこと。変化がなく、同じ事の繰り返しで、未来への希望がない物事の例え。
その他よくある「水」
乜 水
mat1 seui2「乜誰」から変化したという。誰?という疑問ではあるが、少し俗っぽい言い方。多くの場合は「おまえなんて知らない」ような、相手を見下すような意味合いが含まれている。日本語でいうと「どこの馬の骨か分からない」に近い。
苦 水
fu2 seui2日頃の不満や悲しい出来事についての話。愚痴に近いが少しニュアンスが異なる。ちなみに動詞は「吐」で、他の人にそれらについて相談することを「吐苦水」と言う。
心 水
sam1 seui2好みのこと。「啱」とは合っているという意味で、好みであることや、時々好きな物事を「啱心水」と言う。他には思考や考え方のことを指す。例えば冷静で大局を見ることができるのを「心水清」と言われる。
「水文化」と広東語
ここまで非常に多くの「水」を紹介したが、もちろんこれら以外にもまだまだ「水」があり、自由に形を変えられる水のように、様々な意味に化ける広東語の「水文化」と言われたりする。
難しいと感じられる一方、広東語の趣のある魅力の一つでもあるのだ。